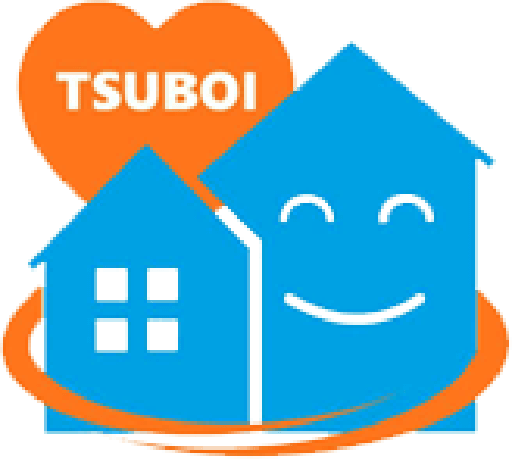STAFF BLOG
スタッフブログ
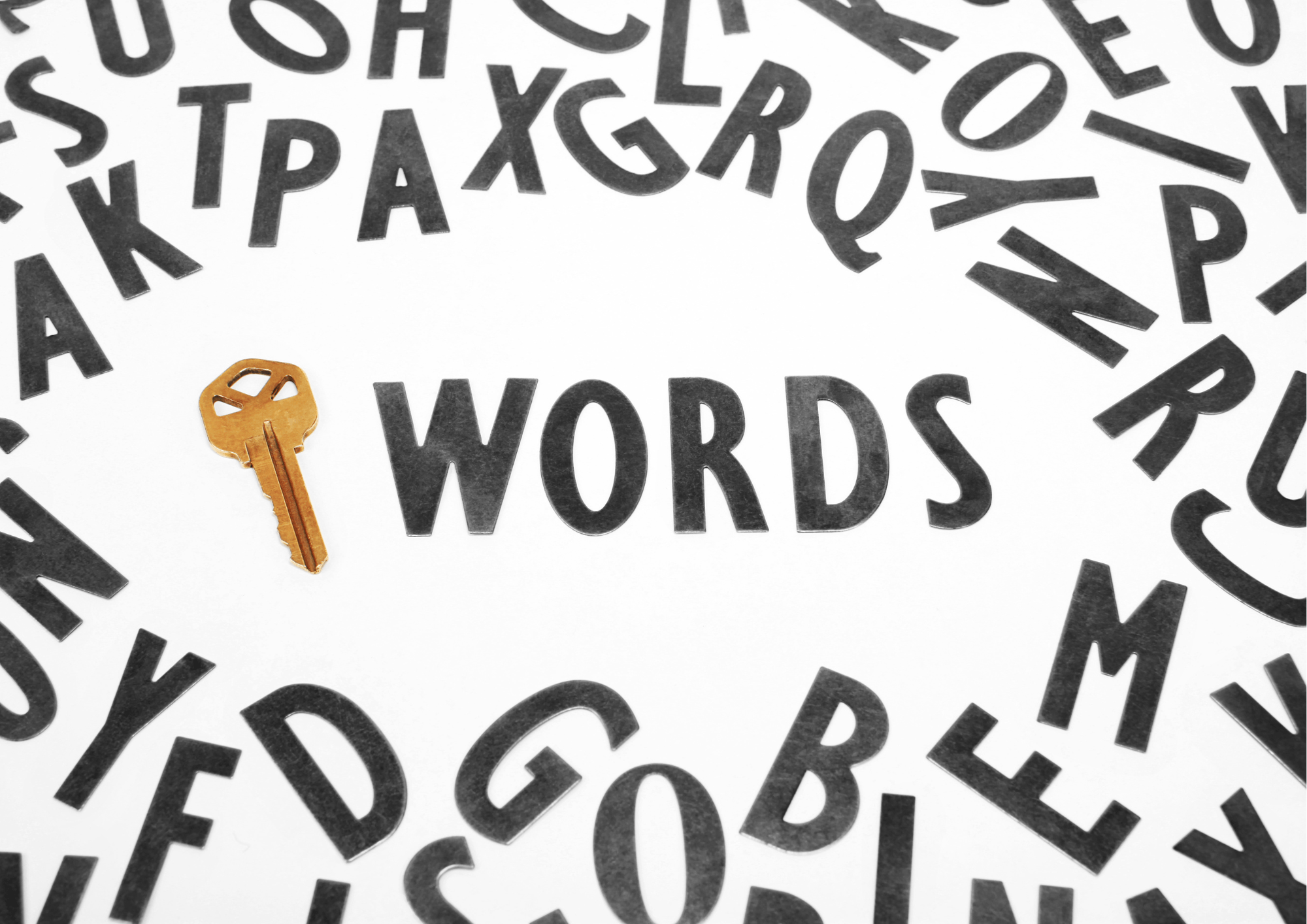
みなさま、こんにちは!
広報企画の田尻です。
梅雨の中休みということでしょうか…
6月からこの暑さで朝から「この夏乗り切れる気がしない…」と少し不安になりながら今日も出勤したのですが、この先7月8月の暑さが心配になります🫠
まだ暑さに慣れていないのもあるとは思うのですが、適切に冷房を使用し食欲が落ちてきている時にもしっかりと栄養のあるものを食べようと改めて感じました!
関西に住んで数年経ったのですが、たまに言われることがあります。
それは「関西弁に染まらないですよね」ということです!
多少イントネーションなどは変わったかもしれませんが、たしかに自分でも東京に住んでいた頃と話し方が変わった気がしていません🤭
それは東京に住んでいた年数の方が長いので染み付いているといえば当たり前のことではあるのですが。
そのようなことや他にも方言について触れる機会が最近多いため、改めて方言ってどうしてあるのだろう?とふと気になってしまいました(笑)
方言がある理由は「言葉は生き物だから」だそうです✨
具体的に言うと
➀地理的な要因
山や川、海などの地理的な障壁があると人々が交流しにくくなり、言葉の変化が地域ごとに独自に進みやすくなる。都のような中心地から遠い地域ほど言葉の変化がゆっくりと進み、古い言葉の形が残ったり独自の変化を遂げたりしやすい傾向がある。
➁歴史的な要因
昔の藩や国の境などが方言の境界線となることがある。それぞれの地域で異なる文化や習慣が育まれ、言葉にも影響を与えたと考えられる。
➂社会的な要因
特定の職業に従事する人々が独自に使うことがある。若者を中心に新しい言葉や言い回しが生まれ、世代間で言葉が異なることがある。かつては、社会階層によって言葉遣いが異なることがあった。
➃言語学的な要因
言葉は常に変化し続けており、その変化の方向や速度が地域によって異なるため方言が生まれる。
それ以外にも物の呼び方に地域の違いがあったりもしますよね!
少し前に九州の会社の投稿がSNSでバズったりもしていたのですが、絆創膏一つをとっても異なります😆
九州ではリバテープと呼ぶ県が多いですよね。
他にもカットバン、サビオと呼んだりする地域があります。
その他にも今川焼を関西では御座候と呼んだり!
関西に来たばかりの頃は御座候ってなんで…?という感じだったのですが、街中を歩いているとなるほどな、と納得しました🚶🏻♀️
肉まんの呼び方の違いも最初は驚きましたよ!
この方言の話を書いていて幼い頃のことを思い出しました。
私の九州の祖母は結構方言バリバリ!という感じでしたので、半分理解できて半分理解できないということもありました(笑)
私が??🤔という感じの反応をしていると祖母は「○○っていうことだよ」と意味を教えてくれたのです。
そのとき「なんで普段方言喋っているのに意味が分かるの?」と不思議に思って聞いてみると「全国放送のニュースをテレビで観ているから」ということ。
幼いながらに納得した覚えがあります(ただの私の思い出話でした🙇🏻♀️)
同じ日本語でも少しずつ異なる言葉の面白さ。
方言は単なる「訛り」ではなく、その地域の歴史や文化、人々の生活様式が反映された貴重な財産ですので、方言を知ることを通してその地域をより深く理解していくのも素敵なことだと感じることができました♪
最後までご覧いただきありがとうございました。
来週のスタッフブログもお楽しみに🙋🏻♀️✨
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私たち住まいるコンシェルジュ ツボイは、常に変化を掴み、
お客様の安心・安全な暮らしを創造し続けます。
■水回りリフォームについてはこちら
■外壁・屋根塗装をお考えの方はこちら
■マンションリフォームお考えの方はこちら